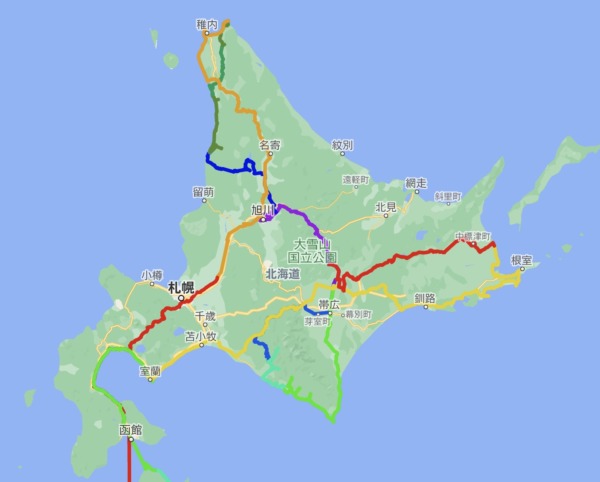【四国八十八ヶ所】志度寺 第86番 花がいっぱいな寺 香川県 さぬき市






志度寺(しどじ/しどうじ)は、香川県さぬき市志度にある真言宗善通寺派の寺院。四国八十八箇所霊場の第八十六番札所。山号は補陀洛山、院号は清浄光院。本尊は十一面観音菩薩。
本尊真言:おん まか きゃろにきゃ そわか
ご詠歌:いざさらば今宵はここに志度の寺 祈りのこえを耳にふれつつ
納経印:当寺本尊、閻魔大王

概要
藤原不比等に関わる伝説は謡曲『海人』で知られる「海女の玉取り伝説」が伝えられており、境内には「海女の墓」が五輪塔群として現存する。また、浄瑠璃の『花上野誉の石碑』(志渡寺の段/しどうじのだん)などの舞台にもなっている。 また、江戸時代、当地の出身の平賀源内を長崎に遊学させるため、当時の住職が尽力したという。本堂の背後で境内の北は志度湾で瀬戸内海が広がり、ひとつ前の札所である八栗寺のある五剣山と屋島が臨める。









歴史
本寺の縁起によると、志度浦にたどり着いた檜の霊木を凡薗子尼(おおしそのこに、智法尼とも)が草庵へ持ち帰り安置し、その霊木から本尊・十一面観音を造立し、小さな堂を建て祀ったという。626年(推古天皇33年)のことで創建とされている。
681年(天武天皇10年)藤原不比等が堂宇を増築し「死度道場」と名づけたという。また、693年(持統天皇7年)には不比等の子・藤原房前が行基とともに堂宇を建立し、寺名を「志度寺」に改めたと伝えられている。この海辺は極楽浄土へ続いているとの信仰を伝えると『梁塵秘抄』に書かれているという。
その後、巡錫に来た、弘法大師が伽藍の修理にあたったのは弘仁年間である。
室町時代には四国管領の細川氏が代々寄進を行い繁栄するが、そののち戦乱により寺院は荒廃する。藤原氏末裔の生駒親正による支援などを経てのち、1671年(寛文10年)、高松藩主松平頼重の寄進(本堂・仁王門)など、高松藩主松平氏により再興された。
1962年(昭和37年)に重森三玲による枯山水「無染庭」が造られている。
伽藍
- 山門(仁王門)- 仁王像を安置。
- 手水舎・鐘楼堂
- 五重塔 – 高さ33m。1973年から着工され、1975年5月に落成。地元出身の実業家竹野二郎によって寄進された。本尊は胎蔵大日如来坐像。
- 奪衣婆堂 – 奪衣婆が拝観できる。脇侍は地蔵菩薩・太山府君
- 本堂 – 毎年、7月16日と17日午前中、本尊と脇仏の開帳をし堂内を見学できる。向かって右奥には凡薗子尼像が鎮座し、宮殿の背後には大きい阿弥陀如来図が直接描かれ、本堂奥の壁には伝持の八祖の掛け軸がかかっている。
- 大師堂 – 以前は中に入れたが、納経所が移動してからは外からの参拝となった。
- 三尊仏 – 阿弥陀・薬師・観音の金属製坐像。藩主松平頼重が切腹させた家来三人を祀る。
- 閻魔堂 – 十一面閻魔大王が鎮座。毎月17日開帳。
- 三社(祠)
- 薬師堂 – 薬師如来坐像を拝観できる。
- 書院 – 浄瑠璃『花上野誉の石碑』の舞台となった。
- 無染庭 – 枯山水庭園。細川勝元によって完成された。納経所の中からも眺めれる。
- お辻の井戸 – 歌舞伎『花上野誉石碑』[注釈 1]に出てくるお辻が水垢離した井戸。無染庭の南側にあり。
- 曲水式庭園 – 室町時代、四国管領であった細川氏によって造成。
- 納経所
仁王門をくぐり、左側の2つ目の通路を行き手水舎と鐘楼堂の間を進むと五重塔の前に出る。その先にある奪衣婆堂を参拝後、右前に進むと本堂があり、その右に大師堂がある。大師堂を背に左に三尊仏があり、進むと閻魔堂がある、さらに進むと三社の祠を過ぎ薬師堂がある。右に曲がり左のピンク色の納骨堂を越えて左側の宝物館と書院の間を入って行くと右側に垣根に囲まれた無染庭があり前方に曲水式庭園が広がる。 無染庭の垣根に沿って右に進んだ先にお辻の井戸が前方にある。薬師堂前の参道に戻り、納経所は書院を過ぎて左手の白壁の蔵との間の小径を入って行くとある。
前後の札所
85 八栗寺 — (6.5km)— 86 志度寺 — (7.0km)— 87 長尾寺
行事
- 藤原房前忌 4月17日[6]
- 柴燈大護摩 5月13日[6] – 護摩法要を屋外の本堂前で執行する柴燈護摩
- 凡園子忌 6月16日[6][11]
- 志度寺の十六度市 7月16日[6] – 海女の命日(旧暦6月16日)にあわせ、境内に市が立ち、また年に1度、本尊十一面観音の御開帳を行う[注釈 2]。
- 藤原不比等忌 8月3日[6]
- 永代土砂加持法要 12月10日[6][注釈 3]
交通アクセス
- 鉄道
- バス
- さぬき市コミュニティバス 「市役所前」下車 (0.7km)
- 道路
- 一般道:国道11号 志度 (0.4km)
- 自動車道:高松自動車道(高松東道路) 志度IC (2.3km)
+++++++++
お花がいっぱいのお寺です。
春から夏にかけての訪問がカラフルです。






















【四国八十八ヶ所】
モフPの体験からの四国八十八ヶ所のすべて
クルマで行くならこちら


セッティング・攻略本
Amazonで出版中
- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録
- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ
- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」
Amazon Kindle無料で読めます。
↓↓Mofp Books
https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて
毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。
現在フォロワー数1300人以上。
YouTube: mofpTV
https://www.youtube.com/@mofptv
日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。
超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。
📚 Mofp Books(Amazon写真集)
旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!
Kindle Unlimitedで読む
SNS
Instagram: @mofmofp_
X (Twitter): @mackenmov
🎮 ゲームセッティング本
GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。
- GT7 セッティング集(100台以上収録)
- GT7 セッティング・バイブル
- EA WRCダートと雪道のセッティング